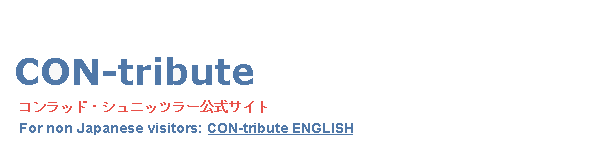
オリジナル・ドイツ語テキスト:Conrad Schnitzler
ドイツ語からの英訳:Gil
Schnitzler
英語からの日本語意訳:Jin
(2007年4月30日)
過去に「どのようにサウンドを聴き、そして何に重点をおいて録音するのか?」と質問されたとき、私はいつも、サウンドやサウンドパターンについての最初の体験を話した。その説明は今まで書き留めたことはなかった。私がどのように聴くか?何を感じるか?サウンドにどのように反応するか?
最初に単独のサウンドがある。私にとって、単独のサウンドとは何か?
単独のサウンドの例とは:
朝起きたとき、夜明けの音が身の回りの音をかき消す。ただし、そのような場合ですら、まったく単独のサウンドがないのに気がつくこともある。夜明けと共に、飛行機が飛び、私が大好きなクロウタドリがさえずり、犬が吠え、トラックが通り、子供の笑い声や近隣の朝の挨拶が聞こえる。
単独のサウンドは、近隣の音なしには、電子機材のスタジオのスピーカーから発せられる音を除いてほとんど存在しない。私は単独のサウンドをヘッドフォーンで聴く。とはいえ、自分の骨が鳴ったりするのをかき消さなければならないが。それゆえ、実際のところ、単独のサウンドは存在しない。いつも、何かしら他のサウンドを伴っている。単独のサウンドへの夢は、夢のままだ。
そのため私は、サウンドを全体的に補う。ミックス・ソロだ。一緒に聞こえる音を受け入れるということだ。ただし、所謂「サウンドの群れ」とは異なるものだが。もちろん、私が12音音階に基づく音楽の話をしているわけではないことは理解してもらっていると思う。これは、音楽ではなくサウンドの問題だ。私の関心事は音楽ではなく、サウンド・イベントだ。私がCDRで作成しているのは、音楽ではなくサウンド・イベントだ。私は音を創り上げる。このサウンド・イベントの世界では、私は「がさつな鍛冶屋」だ。炎とハンマーでもって、荒々しくサウンドを重ね合わせる。
しばしば、私の昔のサウンドの話が語られることがある。何が私をサウンド・イベントに引きつけるのか?私はそれを自分の作品に反映させているか?もちろんそうだ。私が聴いたものは、自分の(潜在)意識の中で明らかになる。私は、意識的に一つのテーマに沿ってプログラムを使わずに音楽を作ったりする。私が幼少期に聴いたものは、脳裏に焼き付けられている。それは、結果として、私が重ね合わせていくサウンド・イベントの中に存在することとなる。大量のミックス・ソロは、一般的に、私が体験したサウンドの記憶の産物だ。
朝起きて雨の中を走る車の音を聞けば、それは車と雨の音となる。私は、避難所を探して地下で座っているときに爆撃音を聞いた。私は、街が焼け、人々が叫び、マシンガンが撃たれ、戦車が走るのを聞いた。私は、周囲の音を聞きながら列車の中で寝た。私は料理をしていたときに、キッチンのノイズを耳で吸収した。私は大きな工場のホールで働き、巨大なサウンドにトランス状態となった。
こうした、数多くの単独のサウンドから成り立つ音はそこいら中にあるが、中でも、衝撃音はかなり大きな音になることがある。例えば、空気ドリルが甲高い音で金属を削るときのスタッカートは人々の気を狂わすほどだが、そのせいで周囲のホワイトノイズはかき消されてしまう。
毎晩、終業近くなると、ほとんどすべての機械が止められ、そのときスペシャルイベントが始まったものだった。工場主任の思惑どおりにはいかず、すべてが同時に止まることは決してなかった。時間をずらしながら止まることによって少しずつ静寂が増していき、そして最後にはすべての動作が完全にストップするのだった。この段階を過ぎると、人々の声や紙のカサカサ言う音、掃除をする音を感じることができた。倍音が消え失せたり、圧倒的な体験といえるホールでのサウンドへの陶酔から冷めるのは、滝の音が消えるのとはまったく違う。誰が列車が近づいてくる音を聞かなかったって? でも列車が離れていくときは、倍の時間、音が鳴り続けるものだ。
私がよく覚えているのは、製造工場のホールごとに存在感のあるサウンドがあったことだ。ホールは並んで建っていて、それらは繋がっていた。ホールの両端には鉄の扉があって、空洞の部屋に繋がっていた。そこは品物をトラックに積み込むのに使われていた。巨大なホールを出て隣のホールへ向かうときに、この空洞の部屋を通り抜けて行くことができる。それぞれのホールには独特のサウンドがあった。かすかに布がサラサラいう音から地獄のような轟音まで、スケールは様々だった。
いつも驚くばかりだったのは、異なるホールで働く度に、いつも他では聞けないサウンドを楽しむことができたことだ。なお、そのときはすべてを脳裏に焼き付けようと意識していたわけではないし、あとでアーティストになってから、それらのサウンド風景を元にサウンド・イベントを創り上げようなどとは考えていなかった。今日そういった作業を行っていると、これらすべての記憶が鮮明に蘇ってくる。
私は、サウンドを組み合わせて作品を作るときに、創造とはこうあるべきだといった原則に従うことは決してない。もし私の美学的なイマジネーションに喜びを与えなかったとしても、ホールからマシンを放り出すようなことはできない。サウンドが私に喜びを与えないからといって、私はそれを叩いたりはできないのだ。サウンドはホールに存在する。それは、なしにすることはできない。ホールのサウンドとは、そういうものだ。
航海時代、私はマシンのエンジニアだったが、船のマシンルームにいたときはどこか事情が違っていた。そこには理想のサウンドというべきものがあった。私はサウンドを聞き、すべてが正常に動作していることを確認した。機能不全がないか聴診器でサウンドを確認することで、私はエンジンのドライブシャフトや一群のマシンをコントロールした。微細なきしみ音、チャープ音、こすれる音、ブクブクいう音、これらは船を停止させる原因と成り得た。そのまま放っておくと、船にダメージを与える原因となり、しいては危険な状態に陥る可能性が出てくるのだ。
コントロール不能に陥るようなダメージの前兆として、通常、そのような異音を耳にするのだ。ピストンがうめき音をあげる場合はスクリューのスピードが速すぎることを示唆してした。それによって船は前進するわけだが、異音は警告音となり得た。このような特別な方法によって、私はサウンドをコントロールすることに慣れていった。
見本市で耳にした不協和音は、私にとってはいい思い出だ。だから、あなたが私のサウンド作品のトーンやノイズを聴くときは、私のイマジネーションの世界を想像してみて欲しい。ただし、それは容易ではないだろう。なぜなら、あなたは私のサウンドに音楽を期待するから。私のミックス・ソロは、伝統的な手法で作曲された音楽とは異なる。それは聴き心地が悪かったりよかったりだが、多くの場合、ほとんど荒削りで難解だ。
これが私のサウンドの世界で、まさに私が生きている空間だ。許して欲しい。だが、私はそれを変えることはできない。
英語原文: A sound never walks alone (about mix solos)
[ CON-tribute JAPANESE ] [ CON-tribute ENGLISH ]
Copyright © 2005-2026 CON-tribute All Rights Reserved.
当サイトで掲載している文章や画像などを無断転載、複製(コピー)することを禁止します。
※詳細はこちら: 著作権・当サイトへのリンク・免責事項・プライバシーポリシー